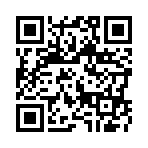2014年10月07日
科学の芽

おつきさま こっちをむいて
片山 令子 ぶん 片山健 え
夕方の公園に遊びに行ったとき、「あ・・おつきさま!」と 豆太郎が空を見上げた。
さあ、帰ろうかという時も、後からついてくる おつきさまを見て、「ふたつあるのかな?
おつきさま?」とつぶやいた。
この本を読みきかせしようかどうか、迷った時期があった。
これは、ちいさな科学絵本。
何となく、「自然にこう思う日を見てみたい・・・」と思ったから、本を置いた。
以前、司書さんに「ちいさなうさこちゃんは、3歳ごろ、人が生まれる

ことに興味がわいてからがいい」と教えていただいて、
その日まで待った。
そう、3歳何か月めかの時、「生まれる」ということに 興味
あるような言葉がではじめた。
自然の不思議さを感じた。

今月号の『母の友』の特集がおもしろい!
「科学の目をもつということ」ということで、科学者の中村桂子さん
と茂木健一郎さんの対談になっている。
自然を「よく見る」ということや、科学という冷たいイメージを払拭して
今の私たちの子育てに役に立つお話が満載だった。
2014年09月24日
おはなしの小道具

昨日夜から、ちょこちょこ縫い始めて、ネズミのぬいぐるみが完成しました。
お話会のプログラムの本の中に書かれてあった『おはなしの大好きなネズミの女の子』をイメージして作りました。
ぬいぐるみを作ったことがないので、雑誌にあったネズミの人形の作り方を見ながら、家に今ある材料を駆使して
なんとかかんとかでき上った感じ。(^_^;)
このお話が大好きで、ぜひ子どもたちに紹介したいけれど、いい感じのネズミの人形がない・・・おはなしの大好きなネズミって
どんなのかな?!とずっと頭にあったので、出来上がってうれしい!!
この女の子が、おはなしの種を見つけて 土に植えます。「お話の木になあれ!」と声をかけると、
新聞紙で作った棒が木に変身します。
工作も交えたこの楽しいお話を、この子と一緒にお披露目できる日を楽しみにしています。

こちらは、10月のお話会で見ることができる、「ととけっこう」のお人形です。
藤田浩子さんの『おはなしの小道具』に掲載されている手袋人形です。
このお話、とってもよくできていて、卵がかえる日数だけ手を叩いたり、ちょっとしたかわいい手品も見られます。
どうぞ お楽しみに~。
2014年09月12日
9月度子どもおはなし会
おはなし会 プログラム
うた たまご たまご
絵本 ぽぽんぴ ぽんぽん (松竹 いね子 文 012絵本 福音館書店)
絵本 おつきさま こんばんは (林 明子作 福音館書店)
うた 「うさぎ うさぎ」にあわせて タオル人形 うさぎ作り
絵本 ぼうしをとってくださいな (松谷 みよ子 文 福音館書店)
絵本 オムライス ヘイ! (武田美保作 ほるぷ出版)
わらべうた このこ どこのこ かっちんこ・おやゆびねむれ・おてぶしてぶし・とんぼとんぼ

おなじみの「たまご たまご」ですが、今回 初めてやりました。
たまごは3つあって
♦♫♦・*:「たまご たまごがぱちんとわれて なかから ひよこが ぴよぴよぴよ まあかわいい
ぴよぴよぴよ」♦♫♦・*:.. これに ありさん、カイジュウと歌詞を変えながら歌います。

ちょうど、お月様のきれいな時期をむかえて、『おつきさま こんばんは』は、しっとりとした読み
手の声に、子どもたちは吸い込まれるように聞いていました。
裏表紙のあっかんべーをしたお月さまの絵が、最後に子どもたちを現実の世界に戻してくれ
て、みんで「あっかんべー」とまねて 2度おいしい絵本でした。
絵本のあとは、♦♫♦・*うさぎうさぎ なにみてはねる じゅうごやおつきさん みて はねる♦♫♦・
と歌いながら、タオルでうさぎを作りました。
今回、紙芝居の代わりに、武田美保さんの「オムライス ヘイ!」をしたのですが、大きな子どもたちが食い入るように オムライスを作っ
ていく様子をみていました。
わらべうたは、大盛況! ここに足を運んでくださるお友達は、0~5歳と わりと年齢にはばがあるのですが、
赤ちゃんとお母さんも、5歳のおにいちゃん達も一緒に楽しめるのが、最大の魅力です。
♦♫♦・*:.このこ どこの かっちんこ♦♫♦・*: と歌い始めると、お母さんは赤ちゃんあやしながら歌い、お兄ちゃんは歌に合わせて体を揺
すります。
その姿が、本当に愛らしい。
2つほど小さい子向けをして、「おてぶしてぶし」 では、お手玉をてにかくしての当てっこをすると、一気に前に出てきて、真剣にどっちの
手に入っているのかを当てに来ます。
最後は、♦♫♦・*:とんぼさん とんぽさん このゆびとまれ ♦♫♦・*と歌い始め、指にとまった 切り紙のとんぼに向けて、指をくるくる回して
いきます。
終わってから、男の子達はおみやげのとんぼを、上から吹き降ろす 室内扇風機で飛ばしてみようと、必死に遊んでいました。
とっても楽しいおはなし会になりました。
ありがとうございました。

にじの会 おはなし会
場所:別府市光の園児童館
日時:毎月 第二木曜日
10時30分スタート
メンバー4人でやっています! 是非遊びに来てくださいね。
うた たまご たまご
絵本 ぽぽんぴ ぽんぽん (松竹 いね子 文 012絵本 福音館書店)
絵本 おつきさま こんばんは (林 明子作 福音館書店)
うた 「うさぎ うさぎ」にあわせて タオル人形 うさぎ作り
絵本 ぼうしをとってくださいな (松谷 みよ子 文 福音館書店)
絵本 オムライス ヘイ! (武田美保作 ほるぷ出版)
わらべうた このこ どこのこ かっちんこ・おやゆびねむれ・おてぶしてぶし・とんぼとんぼ

おなじみの「たまご たまご」ですが、今回 初めてやりました。
たまごは3つあって
♦♫♦・*:「たまご たまごがぱちんとわれて なかから ひよこが ぴよぴよぴよ まあかわいい
ぴよぴよぴよ」♦♫♦・*:.. これに ありさん、カイジュウと歌詞を変えながら歌います。

ちょうど、お月様のきれいな時期をむかえて、『おつきさま こんばんは』は、しっとりとした読み
手の声に、子どもたちは吸い込まれるように聞いていました。
裏表紙のあっかんべーをしたお月さまの絵が、最後に子どもたちを現実の世界に戻してくれ
て、みんで「あっかんべー」とまねて 2度おいしい絵本でした。
絵本のあとは、♦♫♦・*うさぎうさぎ なにみてはねる じゅうごやおつきさん みて はねる♦♫♦・
と歌いながら、タオルでうさぎを作りました。
今回、紙芝居の代わりに、武田美保さんの「オムライス ヘイ!」をしたのですが、大きな子どもたちが食い入るように オムライスを作っ
ていく様子をみていました。
わらべうたは、大盛況! ここに足を運んでくださるお友達は、0~5歳と わりと年齢にはばがあるのですが、
赤ちゃんとお母さんも、5歳のおにいちゃん達も一緒に楽しめるのが、最大の魅力です。
♦♫♦・*:.このこ どこの かっちんこ♦♫♦・*: と歌い始めると、お母さんは赤ちゃんあやしながら歌い、お兄ちゃんは歌に合わせて体を揺
すります。
その姿が、本当に愛らしい。
2つほど小さい子向けをして、「おてぶしてぶし」 では、お手玉をてにかくしての当てっこをすると、一気に前に出てきて、真剣にどっちの
手に入っているのかを当てに来ます。
最後は、♦♫♦・*:とんぼさん とんぽさん このゆびとまれ ♦♫♦・*と歌い始め、指にとまった 切り紙のとんぼに向けて、指をくるくる回して
いきます。
終わってから、男の子達はおみやげのとんぼを、上から吹き降ろす 室内扇風機で飛ばしてみようと、必死に遊んでいました。
とっても楽しいおはなし会になりました。
ありがとうございました。

にじの会 おはなし会
場所:別府市光の園児童館
日時:毎月 第二木曜日
10時30分スタート
メンバー4人でやっています! 是非遊びに来てくださいね。
2014年09月10日
大人のためのお話会
ついに ついに 県立図書館で行われた「大人のためのお話会」 参加してきました!
朝 時間を間違えていることに気が付いて、バッタバタしながら駆けつけ、奇跡的に間に合いました・・・・ Kちゃん ごめんね
第6研修室は、満員です!
一番前が2席 ラッキーにも空いていたので、座って ほっとしたのもつかの間、お話会が始まりました。
演目は かえるの王様 (グリムの昔話)
あなのはなし (ミラン・マラリーク作) おはなしのろうそく4
お月お星 (日本の昔話) 日本の昔話2
江戸の蛙と京の蛙 (日本の昔話) 日本の昔話百選より
ユルマと海の神 (フィンランドの昔話) 『かぎのない箱』より
一時間、おはなしを聴かせていただきましたが、一つひとつが新鮮で、子どもに戻ったような気分になり楽しませていただきました。
ある時、たまたま聴いたおはなしに、脳を揺すぶられるような衝撃を受けました。
それはロシア民話で、その時「ミルクの川、ゼリーの岸」というフレーズを、遠い昔 どこかで聴いたことがある・・・・だけど思い出せな い・・・と、ぐるぐる考えている時に、司書さんの協力をいただき、私が昔 聴いたであろうおはなしにたどり着きました。

何とも言えない懐かしさと、昔の友達に会うような 複雑な心境でした。
私は、読み聞かせなどしてもらった記憶もないし・・・さて どこで聴いたのか・・・。
そのことが、きっかけで 昔話の深い、深い森に足を一歩踏み入れることになったのです。
しかしながら、昔話を辿るということは、本当の意味での民衆の歴史をたどる、私の脳のどこかに、かすかに残る 生まれるもっと前の時代の記憶の旅となりそうです。
小澤昔話研究所 小澤俊夫氏の著作を読むと、興味深い文章に出逢いました。
「歴史というと、学校で習う史実ばかりが歴史と思いがちですが、本当の庶民の歴史は、ひそひそと口伝えされた昔話とか、伝説の中に込められている」と。
子どもに語られる楽しく、悲しい昔話の中にも、人はどう育ち、人はどうやって食べ物を手に入れ、人はどう自然と向き合ってきたのか、そういうメッセージが繰り返し くりかえし伝えられています。
「事実を言えば、子どもの心は純白ではない。
また傍目に見えるほど、彼らはのんきにのんびり生きているわけでもない。
それどころか、自分の気持ちをうまくごまかせないだけで、しばしば、猛烈な苦痛をナマのまま味わう・
死の恐怖、独りぼっちの淋しさ、分離不安、不信、罪悪感、劣等感、屈辱、嫉妬、怨み。
これらの不快な感情が、彼らの内部を渦まく。
昔話は、そういう「内部の現実」を物語ることで、不快な感情の解放をもたらす。
昔話に癒しの効果があるのは、そのせいである」
今 セラピーとか癒しという言葉が氾濫していて、何でもセラピーになっていることがうっとしいと思うのですが、私が、昔話にはまったわけは、きっとこの辺りにあるのかもしれない・・・と考えています。
まだまだ、昔話の森の入り口にたどり着いたばかり。
これからどんなお話に、どんな私に出逢うのでしょうか、と少し楽しみ。
今日、おはなしをしてくださった方々から、宮沢賢治のいう「きれいに透き通った風を、桃色の美しい朝の日光のようなたべもの」をいただきました。
ありがとうございました。
次回は、12月9日(火) 来年3月10日(火)
時間:10時から11時(延長時11時半)
場所:大分県立図書館 一階第六研修室
申込み:不要 どなたでも参加できますが、きっと乳幼児は入れないと思います。
子どものための昔話の語りは、毎月第三土曜にあるようです。
朝 時間を間違えていることに気が付いて、バッタバタしながら駆けつけ、奇跡的に間に合いました・・・・ Kちゃん ごめんね

第6研修室は、満員です!
一番前が2席 ラッキーにも空いていたので、座って ほっとしたのもつかの間、お話会が始まりました。
演目は かえるの王様 (グリムの昔話)
あなのはなし (ミラン・マラリーク作) おはなしのろうそく4
お月お星 (日本の昔話) 日本の昔話2
江戸の蛙と京の蛙 (日本の昔話) 日本の昔話百選より
ユルマと海の神 (フィンランドの昔話) 『かぎのない箱』より
一時間、おはなしを聴かせていただきましたが、一つひとつが新鮮で、子どもに戻ったような気分になり楽しませていただきました。
ある時、たまたま聴いたおはなしに、脳を揺すぶられるような衝撃を受けました。
それはロシア民話で、その時「ミルクの川、ゼリーの岸」というフレーズを、遠い昔 どこかで聴いたことがある・・・・だけど思い出せな い・・・と、ぐるぐる考えている時に、司書さんの協力をいただき、私が昔 聴いたであろうおはなしにたどり着きました。

何とも言えない懐かしさと、昔の友達に会うような 複雑な心境でした。
私は、読み聞かせなどしてもらった記憶もないし・・・さて どこで聴いたのか・・・。
そのことが、きっかけで 昔話の深い、深い森に足を一歩踏み入れることになったのです。
しかしながら、昔話を辿るということは、本当の意味での民衆の歴史をたどる、私の脳のどこかに、かすかに残る 生まれるもっと前の時代の記憶の旅となりそうです。
小澤昔話研究所 小澤俊夫氏の著作を読むと、興味深い文章に出逢いました。
「歴史というと、学校で習う史実ばかりが歴史と思いがちですが、本当の庶民の歴史は、ひそひそと口伝えされた昔話とか、伝説の中に込められている」と。
子どもに語られる楽しく、悲しい昔話の中にも、人はどう育ち、人はどうやって食べ物を手に入れ、人はどう自然と向き合ってきたのか、そういうメッセージが繰り返し くりかえし伝えられています。
「事実を言えば、子どもの心は純白ではない。
また傍目に見えるほど、彼らはのんきにのんびり生きているわけでもない。
それどころか、自分の気持ちをうまくごまかせないだけで、しばしば、猛烈な苦痛をナマのまま味わう・
死の恐怖、独りぼっちの淋しさ、分離不安、不信、罪悪感、劣等感、屈辱、嫉妬、怨み。
これらの不快な感情が、彼らの内部を渦まく。
昔話は、そういう「内部の現実」を物語ることで、不快な感情の解放をもたらす。
昔話に癒しの効果があるのは、そのせいである」
今 セラピーとか癒しという言葉が氾濫していて、何でもセラピーになっていることがうっとしいと思うのですが、私が、昔話にはまったわけは、きっとこの辺りにあるのかもしれない・・・と考えています。
まだまだ、昔話の森の入り口にたどり着いたばかり。
これからどんなお話に、どんな私に出逢うのでしょうか、と少し楽しみ。
今日、おはなしをしてくださった方々から、宮沢賢治のいう「きれいに透き通った風を、桃色の美しい朝の日光のようなたべもの」をいただきました。
ありがとうございました。
次回は、12月9日(火) 来年3月10日(火)
時間:10時から11時(延長時11時半)
場所:大分県立図書館 一階第六研修室
申込み:不要 どなたでも参加できますが、きっと乳幼児は入れないと思います。
子どものための昔話の語りは、毎月第三土曜にあるようです。
2014年09月04日
大人のためのブックトーク
ブックトークとは、幼児ではなく、小学校中学年以上~大人に対して、ある一つのテーマにそって、数冊の本を順序良く、上手に紹介すること。
目的としては、子どもたちに「その本を読みたい!」という気を起こさせる・著者や関連分野について興味を持たせる。
「読書」が新しい世界の考えや経験を探る道・・・・・という楽しさを知らせる。
ん~、素晴らしい!!
あれだけ小さいときから絵本読み聞かせてきたのに、今は隣で漫画読んでる娘に、誰かブックトークしちょくれ~~~
大体、読み聞かせが各地域で定着してきたからか、中高生の読書人口の激減からか、今年 県立図書館の講演会・講座はブックトーク一色。
この前 東京こども図書館の張替恵子氏による、講演会+ブックトーク実演に参加してきましたが、素晴らしすぎて言葉がなかった。
あくまでも本のプレゼンであってパフォーマンスではない「図書館員のアート」と言い切った、迫力のブックトーク。
聴いて、初めに思ったのは、普通の読み聞かせのおばさんレベルじゃ、たいしたブックトークはできない・・・ということ。
実際本が好きで かなり読み込んであって、これを誰かに伝えたいという並々ならぬ情熱、まさにアートまで持っていく意気込みがないと、今のスマホに夢中の中高生の心には響かない。
これからは 子どもたちの図書館離れを食い止める 職員の使命かもしれませんねぇ・・と先輩方と話をした。
私自身は、今は読み聞かせの活動をしているが、小さいころから本好きで・・・という事ではなく、外で野山をかけ回って遊んだくちで、娘を産んだのおかげで絵本に出会い、読み聞かせに出会い、この頃ちょぼちょぼ本を読んでいる位なので、今の中高生に「これ ステキな本だよ!」と勧めるネタをほとんど持っていない。
絵本も読んだのは「ちびくろさんぼ」ぐらいしか記憶になくて、幼年図書も「ふしぎな鍵ばあさん」とか数冊。
なので、今 本当に児童文学が好きで読み込んでいて、その魅力を語れる人のブックトークをぜひ聴きたい!と思う。
今月も9日に「大人のためのお話会」で語りを聴くことはできるけれども、ぜひ「大人のためのブックトーク」、あったらいいな・・・と。
今まで目にはしていても、観たことがなかったNHK『100分で名著』。
夏に放送された「遠野物語」からかなりはまってみている。
一冊の本を4回にわたって解説し、 専門家を招いて 見事な大人のブックトークが見られる。
本来のブックトークとは、少し違うのかもしれないけれど、司会者の感想や想いが語られていて、そこも本への興味や魅力を増してくれる。
もう秋はそこまで来ていて、読書にもいい季節になりますわ。

目的としては、子どもたちに「その本を読みたい!」という気を起こさせる・著者や関連分野について興味を持たせる。
「読書」が新しい世界の考えや経験を探る道・・・・・という楽しさを知らせる。
ん~、素晴らしい!!
あれだけ小さいときから絵本読み聞かせてきたのに、今は隣で漫画読んでる娘に、誰かブックトークしちょくれ~~~
大体、読み聞かせが各地域で定着してきたからか、中高生の読書人口の激減からか、今年 県立図書館の講演会・講座はブックトーク一色。
この前 東京こども図書館の張替恵子氏による、講演会+ブックトーク実演に参加してきましたが、素晴らしすぎて言葉がなかった。
あくまでも本のプレゼンであってパフォーマンスではない「図書館員のアート」と言い切った、迫力のブックトーク。
聴いて、初めに思ったのは、普通の読み聞かせのおばさんレベルじゃ、たいしたブックトークはできない・・・ということ。
実際本が好きで かなり読み込んであって、これを誰かに伝えたいという並々ならぬ情熱、まさにアートまで持っていく意気込みがないと、今のスマホに夢中の中高生の心には響かない。
これからは 子どもたちの図書館離れを食い止める 職員の使命かもしれませんねぇ・・と先輩方と話をした。
私自身は、今は読み聞かせの活動をしているが、小さいころから本好きで・・・という事ではなく、外で野山をかけ回って遊んだくちで、娘を産んだのおかげで絵本に出会い、読み聞かせに出会い、この頃ちょぼちょぼ本を読んでいる位なので、今の中高生に「これ ステキな本だよ!」と勧めるネタをほとんど持っていない。
絵本も読んだのは「ちびくろさんぼ」ぐらいしか記憶になくて、幼年図書も「ふしぎな鍵ばあさん」とか数冊。
なので、今 本当に児童文学が好きで読み込んでいて、その魅力を語れる人のブックトークをぜひ聴きたい!と思う。
今月も9日に「大人のためのお話会」で語りを聴くことはできるけれども、ぜひ「大人のためのブックトーク」、あったらいいな・・・と。
今まで目にはしていても、観たことがなかったNHK『100分で名著』。
夏に放送された「遠野物語」からかなりはまってみている。
一冊の本を4回にわたって解説し、 専門家を招いて 見事な大人のブックトークが見られる。
本来のブックトークとは、少し違うのかもしれないけれど、司会者の感想や想いが語られていて、そこも本への興味や魅力を増してくれる。
もう秋はそこまで来ていて、読書にもいい季節になりますわ。