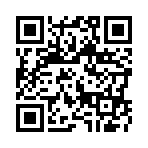2014年09月08日
今日のおさんぽ

朝 おひさまが出ている。
そして空には 秋のうろこ雲。
ここ2か月、曇り もしくは雨の毎日で、朝からこんなに気分のいい天気は久しぶりだった。
豆太郎に散歩に行こう!と声をかける。 幼稚園に行くようになってからお散歩は久しぶり。
バスが来るまでは、まだ一時間以上もある。
なぜか戦隊もののおもちゃを抱えて、公園までの道を歩く。
公園は、草 ぼうぼう。 ここのところの雨・雷で、こういう作業も進んでないんだろうな・・・・
そして、蚊・・・ ほとんどここに遊びに来る子どもたちも今 いないのか、待ってましたとばかりに、襲ってくる。
東京でのデング熱の一件で、なんかヘタしたら一年中悩まされるここらの地域の蚊が気になってしまう。
朝で だあれもいないし、草ぼうぼうっぷりが気に入らないのか、豆太郎も「帰ろう・・・」というので、ちょっと遠回りして おさんぽしながら帰る。
 ちょっと前までは、よく歩いてくれたけれど、ここ2,3か月で、一歳児に戻った ように歩かなくなった豆太郎。
ちょっと前までは、よく歩いてくれたけれど、ここ2,3か月で、一歳児に戻った ように歩かなくなった豆太郎。最近子どもと「歩くこと」について 『母の友』にあった文章を思い出す。
文部科学省が行う「体力・運動能力調査」を見ると、30年前の調査よりも格段
落ち込んでおり、今 下げ止まり状態であること。
体力が落ちたということよりも深刻なことは、数値では現れない 子どもの「動
き」の変化が観察されるということ。
「転んだときに手をつけない」 「すぐ疲れたという」「顔にけがをする」等々。
日常生活の中で、当たり前のように身につけていくべき『動き』の習得ができていないのである。
子どもが体を動かさなくなった理由として、遊びのカタチが変わり、30年で運動量は半減。 現在お悩みのお母さんも多いと思いますが、外で「鬼ごっこ」「かくれんぼ」をしていた時代から、室内でゲーム、外でもゲームと、体を動かすことが極端に少なった。
ライフスタイルも変わり、女性の出産年齢が上がり、親になるまでの外食、買い物、旅行などの経験の豊富さから、出産後も子どもに合わせて変えるのではなく、今までと同じスタイルを保とうとする人が増えたということ。
野外の遊び場が減少。 「都市化」が大きく進み、住宅地の周りにあった空き地や野山が減りました。
交通量が増え、交通事故や防犯意識の拡大で、外で自由に遊ばせることが少なくなったこと。
時代を巻き戻すことはできませんが、もう少し、「歩くこと」や「外遊び」のことを考えてみようと思います。
幼児期に動きの基礎が出来あがる・・・・ 幼児から小学生にかけて体を動かすことが大事だといわれる理由の一つは、「動き」を作る神経系の発達が著しいため。
神経回路は、3歳前後までに急速に発達し、大人の60%まで出来上がるといわれています。
この時期に たくさん歩くと、土ふまずが形成され、けがをしにくい体になり、バランス感覚も養われます。
大人もウォーキングが盛んにされていますが、子どもたちも「歩く」ことで、様々な刺激を受け、発達していきます。
子どもに必要なのは、スポーツではなく「遊び」・・・・大人の指導の下、体を動かすことと、自由に遊ぶことの違いは、「楽しいから動き回る」というメンタルな部分と、一日中いろんな遊びを通して、自然と「動き」が身についてくる、そして遊びがさらに楽しくなりもっと遊びたくなる。という よい循環が無理なく自然と生まれる」(『母の友』2012年10月号 「だいじょうぶ? 子どもの体力」より)

こう書きながらも、私たちが育った 野山で自由に駆け回った時代とは違い、お姉ちゃんの周りの環境も、かなり淋しいばかり。
公園には誰もいない、近くに遊べる友達も少ない。
よく、ゲームがなかったら友達と何をしていいのかわからない・・という言葉を聞くと、本当に悲しい気持ちになる、という親御さんも少なくないと思う。
だから、今 3歳の息子との「おさんぽ」の時間が愛おしくてならない。
夕方、お姉ちゃんも誘って、おさんぽに行く。
おさんぽに行けば、ゲームに夢中の姿とは、また違った、娘らしい本来の愛らしさが見えてくる。
弟を気遣う、成長した娘の姿も。
何となく、夏の置き土産のセミの声や、秋の虫たちの声、草花を見ながら、「歩くこと」を一緒に楽しんでいきたい。